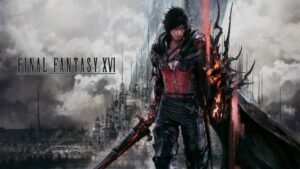➤評価別
➤ハード別

先日とある投稿をXで目にした

10年後は任天堂とPC(Steam)しか残ってないんじゃね?
面白い仮説だが、俺はどうにも納得できなかった。もしPlayStationがPCに取り込まれたとして、本当に任天堂は生き残れるのだろうかという疑問が拭えなかったのだ。
たしかに任天堂のIPの強さは疑いようがない。マリオ、ゼルダ、ポケモン。どれも世界的なブランドであることは間違いないが、最近の任天堂を見ていると「それPCでよくね?」と突っ込まれてしまう未来が近づいているように感じてしまうのだ。
今回はそんな「もしも」の話をもとに、なぜ俺がそう思ったのかについて話していきたいと思う。
近年の流れを見ているとPlayStationやXboxは限りなくPCに近しい存在になりつつある。
PCに対する価格の安さや、統一された規格であるゆえの安定性などメリットは多数あるが、ゲームの体験としてそれぞれを差別化できる要素は独占ソフトぐらいしか残っていない。
だからこそPlayStationやXboxはその「ハードでしか遊べない」という付加価値である独占ソフトを用意するわけだが、昨今のゲーム開発には莫大な金額がかかるため単一のプラットフォームではその開発費を回収しきれないのが実情。
だからサード各社のゲームは積極的にPCへの展開が行われている。それはPlayStationの母体であるSIEとて例外ではなく、ゴッドオブウォー、ホライゾン、ラストオブアスなどのPS5のファーストタイトルまでもがPC向けに発売されている。
そこには「より多くの人にゲームを届けたい」という思いももちろんあるだろうが、ゲーム機にとって独占ソフトを手放すことは付加価値を失うのと同義なので、100%善意でPCへの展開が行われているわけではないことは間違いない。
PS5というプラットフォームに価値があることは間違いないが、その中身は限りなくPCに近い存在になりつつある。XboxはすでにPCとの融合を始めており、ゲーム機とPC、両者の境界が曖昧になることで「PC取り込まれる」という表現は一理あるかもしれない。
では任天堂はどうなのか。
Switch2に対する俺の率直な感想は「極めてPC寄りのマシン」になったというもの。Switch2はざっくり言えば「Switchの性能強化版」で、ゼルダやポケモンが60fpsで遊べることや4K出力に対応したなど「性能の進化」が最大の売り。
一方で携帯モードでは性能向上と引き換えに大型化して重くなり、バッテリー持ちも悪くなるなど先代Switch最大の売りであったはずの携帯性という強みが弱体化してしまっている。マウス操作も新しい挑戦ではあるがそれこそPCの体験となんら変わらないし、テレビに繋いだら結局コントローラーを使うという制約もありこれまたPC的な体験に寄っている。
その結果Switch2は「任天堂IPを遊ぶためだけの箱」という側面が強くなってきているように感じている。しかも高性能化によってこれまで任天堂の美学と考えられてきた「制限された中での遊びや創造性」という理念すら揺らぎ始めている気がしてならない。
これまではユーザーたちにこの理念が広く受け入れられてきたことで、任天堂は性能競争から一歩引いた独自の立ち位置を確立してきた。ゲームの楽しさはグラフィックや性能ではない。ハードスペックに依存しない体験こそが任天堂ソフトの価値だと誰もが思っていた。
しかし事実としてユーザー達はSwitch2の性能向上を受け入れ大絶賛している。ゼルダやポケモンが高画質になり60fpsでぬるぬる動いているのを見て感動している人もいた。クリエイターですら「Switchではできなかった表現がSwitch2ではできた」などスペック向上による恩恵を受け入れる声が上がっている。
この事実は例の美学とは明らかに矛盾しており、もはや任天堂の独自の立ち位置は崩壊しつつあることを意味している。多くの人間に性能が求められている、それはPS5やXboxと何ら変わりない。今回のSwitch2は極めて普遍的なハードになったと言っていいだろう。
Switch2が発表される前はよく思っていた。

ゼルダをPS5でやりてえなあ
ありえないけどさ、マジでありえないけど、もしブレワイやティアキン、ポケモンSVがPCやPSで発売されたらって想像してみてほしい。
4K60fpsで動く高精細なハイラルの世界を自由に冒険できて、もしかしたらもっと色々な天気があったりさ、地震が起きたり敵の攻撃で地形が変化したりさ、そういった不確定要素も楽しそうじゃない?
ポケモン達が生きる広大な世界を、自分の好きな相棒と空を飛んだり海を泳いだりしてさ、そこを歩いてるだけで美しいポケモンの世界に触れられるかもしれないよ。
空や地下空間はもちろん、水の中とか宇宙とか、そんな新しい表現が生まれるかもしれない。それってめちゃめちゃ魅力的だと思わない?
と、ユーザーに思わせてしまうあたり、かつてあったはずの「任天堂らしさ」が弱くなってきているなと感じてしまう。
任天堂はこれまで「そのハードでしかできない遊び」を提供することでゲーム業界で存在感を示してきた。DSの上下二画面、タッチ操作、マイク入力。Wiiリモコンの体感操作。どれも「他では真似できない体験」を実現してきた。
Wiiのゼルダの伝説 スカイウォードソードはリモコンが剣、ヌンチャクが盾という体感型に全振りした尖った作品で、リモコンの傾きを検知する仕掛けがあったのはとても斬新だったし、強敵との歯応えのある戦いには胸が熱くなった。
今でも感動しているのはDSで発売された「 夢幻の砂時計」と「大地の汽笛」だ。攻略のヒントをプレイヤー自らマップに書きこんだり、タッチ操作や息を吹きかける仕掛けが印象的だったが、そのなかでも「海図をうつす」という仕掛けは間違いなくDSにしかできない演出と体験だったと断言していいだろう。
そういった替えの効かない体験こそが、任天堂が唱える「ハード・ソフト一体型」の根本だと思っている。
じゃあ「Switchじゃないと成立しない体験」って何があるだろう。
ジョイコンを分け合って遊べるという機能もあるが、それはあくまで遊び方のひとつであってSwitchで遊べるゲームの「体験の核」とは言い難い。
となるとSwitchでしか味わえない独自の体験…それはジョイコンを使った体感的な操作だが、ジョイコンをフルに活用したタイトルは意外と少数。
確かに存在はしているがその数は少ない。そのなかでも著名なタイトルに絞るとさらに少なくなる。
一方でSwitchの売り上げを牽引してきた求心力の高い主力タイトルと呼べる作品達
これらは全てコントローラー操作だけで成立する。携帯モードの時を除いてプロコンさえあれば何も困らない。つまり「Switchにジョイコンって本当に必要なのか?」という状態なのだ。
そしてこれは現状のSwitch2でも同じで、すでに発売されている
・マリオカートワールド
・ドンキーコングバナンザ
この2作もコントローラー対応。
独自の武器であるジョイコンを活かした作品とは言い難い。こうなってくると、任天堂がかつて持っていたはずの「そのハードだからこそできた体験」という軸がかなり弱くなってきている。
その結果任天堂の独占ソフトは「任天堂ハードでしかできない遊びがあるから」という唯一無二の体験に由来していたものから「自社IPだから」という商業的なものに変化してきている。
DSゼルダのギミックやスカイウォードソードの剣を振る体感操作、あれはまさにハードとソフトが一体化しており「このハードでしかできない体験」を提供していたが、Switchを代表するタイトルの9割はコントローラーで遊べてしまう。
そう。現在のマリオ、ポケモン、ゼルダは任天堂のソフトだからSwitchで遊べるというだけで「Switchでなければできない体験」ではなくなっているものが殆どなのだ。テレビの前に座って遊ぼうが、ベッドの上に寝転がって遊ぼうが、そこで得られるゲーム体験は普遍的なものだ。
そんなSwitchの後継機であるSwitch2は、ソフトの高画質化や60fps化といった性能の向上がメイン。つまり、コントローラーで遊ぶゲームのパフォーマンスが上がったことがSwitch2最大のメリットであり特徴なのだが、その進化の方向性はPS5やXboxと全く同じだ。
持ち運べるという特徴も本体の性能向上と大型化によって弱体化し、昨今のUMPC市場の賑わいから見ても携帯型のゲーミングPCも今や珍しくはない。そういった独自の体験が希薄になったSwitch2は他社と同じく、極めてPCに近い存在へと変わりつつある。
しかしそれはWiiUの手痛い失敗から学び、サードパーティを巻き込むために普遍的なハードへの進化を選んだ結果なので、ある意味必然ともいえる。
そんな任天堂がどうやって普遍化したハードに付加価値をつけるか。ジョイコンをフルに活かしたタイトルがほとんど存在しない、あるいは活用するのが難しいのであれば「自社ソフトの独占」によって付加価値をつけるしかないのだ。

それでも任天堂はIPが強いから大丈夫
確かにマリオ、ゼルダ、ポケモンといったキャラクターのブランド力は絶大だ。しかし問題は先程から述べているように 「そのIPが本当に任天堂ハードでなければ遊べない体験を提供しているのか?」 という点だ。
結局のところ、コントローラーで遊ぶスタイルが中心でジョイコンをフル活用したゲームは少数派だ。ジョイコンをおすそ分けできるという特徴はあれど、それがSwitchのゲームそのものに影響しているとは言い難く、その殆どは「PCでも実現できる」ものになっている。
Switch独占だった「デモンエクスマキナ」はかなり動作の重いゲームだったが、PCに移植された際はその推奨スペックの低さから殆どのPCで圧倒的に快適な動作が可能だった。それはつまりSwitchソフトは他社ハードやPCでの快適な動作が約束されているということの証左だ。
そしてその新作は最初からPS、Xbox、PCへのマルチ展開。それぞれが所持する環境で遊べてしまうのだから当然だが、これによって同作を遊ぶためのハードウェア選びにおいてSwitch2を選択する理由が一つ減ってしまった。
これが意味していることとは何か。
それはコントローラーを握って遊ぶという普遍的なゲーム体験において「任天堂ハードでなければならない理由」はどこにも無いということだ。ゼルダやポケモンが現行の操作感ならPCやPS5で動いていても何も不思議ではないだろう。
つまり「独自体験がないIP独占」は、結局「囲い込み」以上の意味を持たないのだ。
そしてもうひとつの大きな問題は開発費の高騰だ。参考までにSwitchのマリオカート8DXのDL版は6,578円だが、Switch2のマリオカートワールドのDL版は8,980円とかなり高額化しており、これはPS5で展開されているAAAタイトルにも匹敵する価格となっている。
これまでの任天堂ソフトの多くは約6,000〜7,000円辺りで販売されていたため、任天堂のファーストパーティでこの価格はかなり高い。今後Switch2で発売される大型のタイトルは安くても7,000円以上、大型タイトルなら8,000〜9,000円近い価格になるかもしれない。
4KになるとフルHDでは省略されていたアセットの作成やテクスチャの描き込み、キャラクターや背景のディティールの細かさなど、Switchの頃とは比べ物にならないほどの作り込みが必要となるため、それによって開発費が上がることは避けられない。
結果Switch2のソフト価格は前世代よりも上昇しているし、Nintendo Onlineの強みだったソフト2本で9,980円という超お買い得な「カタログチケット」も廃止された。それは間違いなくゲーム開発のコスト上昇を意味している。
知ってのとおり肥大化したゲームの開発コストは、もはや単一のプラットフォームでは回収しきれない。
それこそがPlayStationが現在抱えている最大の問題であり、それを解決するためにPC市場に独占ゲームを展開しているわけだが、それをすると世間から何を言われるか。
そう

それPCでよくね?
なんだよね
PlayStationの独占タイトル達はコスト回収のために”泣く泣く”PCに移植され、果てには「なら最初からPCでいいじゃん」などと言われてしまうこの構図は、同じ道を辿っている任天堂が今後直面しかねない現実なのだ。
コントローラーを握って遊ぶという普遍的な体験を提供している限り、それは他のハードやPCでも替わりの効くものである事に変わりはない。「IPが強いから」というだけで任天堂ハードが生き残る保証などどこにもないのだ。
もしも任天堂が現在の姿勢を続けるのであれば、やがて他のハードと同じようにPC化という大きな流れに呑まれてしまうのも時間の問題だ。PS5もXboxもSwitch2も「PCに近づいている」点では同じだ。独占ソフトという概念も、もはや他社との差別化のためだけに存在しているに過ぎない。
ではそのうえで任天堂が「それPCでよくね?」を回避するためにはどうすればいいのか。
その答えはシンプルで、やはり任天堂ならではの「尖った体験」 を提供し続けるしかないだろう。ジョイコン両手持ちをフルに活かした体感ゲームでもいいし、まったく新しいギミックでもいい。DSのゼルダやWiiのスカイウォードソードのように「このハードじゃなきゃダメだ」という説得力を持たせる必要がある。
「自社IPだから」という概念的な独占理由ではなく「ここでしかできない体験があるから独占」という物理的な理由を取り戻さなければならない。
しかし現実的な話、開発費の高騰したゲームは平凡化を招いてしまう。業界人の間でしばしば囁かれている「AAAタイトルはどれも似たり寄ったり」というのがこれだ。莫大な開発費を投じたAAAタイトルに失敗は許されない。つまり安定した面白さが求められるため、失敗を恐れて大きな挑戦がしづらくなる。
斬新な発想はリスクとされ保守的な作品が増えていき、どれも似たり寄ったりな作風になっているという状況だ。そういった流れに足を踏み入れた任天堂が、今後の大型タイトルで「挑戦的で尖った体験」で勝負していくのは万が一にもコケた時のリスクが高すぎる。かといって現在のような普遍的な体験の作品ばかり作っていては「それPCでよくね?」と言われかねない。
大型タイトルの開発費を考えると単一のプラットフォームでのコスト回収は難しい。かといって前向きな独占を維持するために「尖った体験」に挑戦するのもリスクが大きい。それならばいっそのこと大型タイトルは普遍化を強め、他機種に展開してもいいのではないだろうか。
実際Switchで発売されてきたゼルダやポケモンなどの主力ソフトは、任天堂独自のギミックを活かした体験を抜きにしても数千万本を売り上げている。普遍的な体験であるとはいえ、それが多くのユーザーに評価されているのも事実。任天堂はハードウェアメーカーであり優秀なソフトメーカーでもあるのだ。
ブレワイやティアキンが任天堂の独占を解かれ、より高スペックなマシンで動作することが可能になれば、間違いなく売り上げは更に伸びるだろう。任天堂は大型タイトルの普遍化をあえて強めることで、他機種に展開してソフトの販売利益を最大化しつつ、これまでハード性能によって実現不可能だった表現や遊びを提供することも可能ではないだろうか。
その傍で任天堂ハードではあくまでもサードを巻き込むことは考えず、小〜中規模なタイトルで体感操作を活かした「尖った遊び」を追求していくべきだ。
特に低予算タイトルは独自体験を追求する場として大いに活かせるだろう。失敗のリスクは小さく、成功すれば「やっぱり任天堂は面白いゲームが作れるんだ」とブランド価値も引き上げられる。
大型タイトルを他機種でも展開しつつ利益を確保し、自社ハードのギミックを活かしたタイトルをしっかりと作り込むことで任天堂ワールド専用の「玩具箱」のような存在を確立させるのだ。
そうすれば任天堂ハードは独自の立場を確立し、PC化の流れに呑まれる事なく生き残ることができるだろう。
今回の話をまとめると
今後の任天堂に求められるのは、二つ
任天堂は「IPの強さ」だけではなく「遊びのデザイン力」で存在意義を示さなれば、やがて訪れるPC化の奔流に呑まれてしまい、最終的にはソフトメーカーと化してしまうだろう。
とまあ、ここまで話してきたけど、実際のところ俺はゲーム機はどんな形であれ残ると思っている派だ。仮にPCが主流になっていったとしても、エントリー向けを謳うゲーム専用の製品は必ず出てくるだろう。複雑化した汎用機よりも簡単に扱うことのできる専用機は、ユーザーとクリエイター双方にメリットがあるからだ。
単一のプラットフォームはクリエイターにとって開発がしやすいのは言うまでもないが、汎用機と専用機は動作安定性も全く違うし導入コストもPCに比べて安いため、比較的お金をかけずに十分満足のいく環境でゲームを楽しむことができる。PS5、Xbox、Nintendoのいずれにおいても、IPではなくその手軽さこそがゲーム機という専用機の価値だと俺は思っている。
Switch2は売れるだろう、独占IPの強さは圧倒的だしそれは間違いない。しかし「任天堂ハードでしか味わえない体験」が弱まっているのも事実だ。普遍化が進むハードの上で「消極的な独占」に依存している限り、PCとの差はどんどん縮まっていくだろう。
俺はやっぱりWiiリモコンでマスターソードを振ったあの感覚、DSで画面を閉じて謎を解いたあの驚き、そういう「尖った体験」を提供してくれる任天堂をもう一度見たい。普遍的なプラットフォーム提供者やソフトメーカーとしてではなく、ハードとソフトが一体となった驚きをまた見せてほしい。
「それPCでよくね?」と誰もが思ってしまう前に「遊びをデザインする会社」としての任天堂をもう一度見てみたい。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!